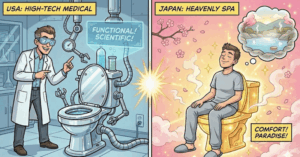江戸から続く「仕掛け」の始まり
夏になると、スーパーやコンビニの店先には「土用の丑の日」と書かれたのぼりが立ち並びます。
ふだんはあまり食卓に上らないウナギも、この日ばかりは特別扱い。
うな重やかば焼きが並び、家族そろって「夏バテ防止に」と口にする光景は、すっかり日本の夏の風物詩となっています。
けれども、そこで一つの疑問が浮かびます。
実はウナギの旬は秋から冬。
脂がのって最も美味しいのは寒さが深まる季節なのです。
ではなぜ、日本人はあえて旬ではない真夏にウナギを食べる習慣を持つようになったのでしょうか。
その背景には、江戸時代を生きた一人の奇才が仕掛けた、日本最古の「マーケティング戦略」が隠されているといわれています。
土用の丑の日とは?
「土用の丑の日」といえばウナギ。
あまりに定番過ぎて「ウナギ専用の祝日」と勘違いしても不思議はありません。
けれども暦上の本来の意味は、全く別のものです。
「土用」とは、古代中国の五行思想に基づく暦の区分で、四季の終わりにあたる約18日間を指します。
つまり、立春・立夏・立秋・立冬の直前には、それぞれ「土用」があるのです。
年に4回もやってくるのですから、「土用の丑の日」は実は夏だけの特別イベントではありません。
では「丑の日」とは何でしょうか。
これは、日付を十二支で数えていた時代の名残です。
12日ごとに「子」「丑」「寅」……と巡っていくため、土用の期間に重なった丑の日が「土用の丑の日」と呼ばれるようになりました。
年によっては土用に2度丑の日がめぐってくることもあり、そのときは「一の丑」「二の丑」と呼び分けました。
現代人からすれば、「おかわりまであるのか」と笑いたくなるところです。

さらに、この丑の日には古くから「う」のつく食べ物を口にすると夏負けしない、という食養生の習慣がありました。
梅干し、瓜、うどん……なるほど、どれも精がつきそうです。
そして、この「う」の仲間に後から加わり、ついには主役にまでのし上がったのが、あのウナギだったのです。
では、どうして数ある食べ物の中から、ウナギが主役の座を射止めたのでしょうか。
なぜ土用の丑の日にウナギを食べるようになったのか?
ウナギそのものは、実は縄文時代から食べられていました。
5,000年前の貝塚からも骨が出土しているほど、長い付き合いの食材だったのです。
ただし、旬は秋から冬。
夏のウナギは痩せていて味も落ち、江戸時代の人々にとっても売れ行きの悪い品でした。
ここで登場するのが、江戸の奇才・平賀源内です。
発明家にしてコピーライターの元祖ともいえる彼が、知り合いの鰻屋から「夏に売れない」と相談され、店先に「本日土用丑の日」と大書した看板を掲げさせた ── そんな逸話が残されています。
まるで現代のインフルエンサーがSNSで仕掛けるように、江戸の町では「丑の日にはウナギを食べるべし」というメッセージが一気に広がっていったのです。

この「平賀源内仕掛人説」はきわめて有名ですが、実のところ後世に伝わる逸話に過ぎず、確証は残されていません。
ただ、『明和誌』(1822年)には、土用の丑の日にウナギを食べる習慣が安永・天明期(1772〜1789年)に始まったと記されています。
これはまさに源内の活躍期と重なります。
直接の裏づけこそないものの、「源内ならやりかねない」と思わせる奇才ぶりが、この説をいっそう魅力的にしてきたのでしょう。
もちろん、他の説もあります。
江戸の鰻屋・春木屋が、丑の日に焼いた蒲焼きだけが日持ちしたことから「土用丑の元祖」を名乗ったという話。
あるいは狂歌師の大田蜀山人が「丑の日にウナギを食べれば夏負けしない」と詠んで広めたという説。
いずれにせよ、共通しているのは「夏は売れないウナギを、あえて旬外れの時期に売り込んだ」という逆転の発想です。
この仕掛けは、しばしば「日本最古のマーケティング成功事例」と称されます。
そしてその波は、明治から昭和、平成、令和へと途切れることなく受け継がれ、今もなお夏の習慣として根付いています。
もっとも、源内本人も、自分のアイデアが二百五十年後にスーパーのチラシを賑わせるとは夢にも思わなかったでしょう。
絶滅危惧種になった夏の主役
いまや日本のウナギ消費は、まるで夏の花火大会のように「土用の丑の日」に集中しています。
統計によれば、年間消費量の実に4割がこの一日に吸い込まれるのです。
江戸の町人が聞けば、「いくら源内でも、ここまでやるとは思わなかった」と腰を抜かすに違いありません。
2000年には消費量がピークを迎え、日本一国で世界の七割を食べ尽くすほどでした。
その後は減少したものの、いまでも日本は世界有数の「ウナギ大国」です。
お祭り気分の裏側で、ウナギ資源はじわじわと追い詰められてきました。

2014年、国際自然保護連合(IUCN)はニホンウナギを絶滅危惧種に指定しました。
つまり、あの甘辛い香りが漂う蒲焼の裏側には、「このままではウナギがいなくなるかもしれない」という警告がつきまとっているのです。
問題はさらに深刻です。
養殖に使う稚魚シラスウナギの取引は不透明で、違法漁獲が混ざることも珍しくありません。
完全養殖の研究は進んでいますが、コストが高く、庶民の食卓にのるにはまだ遠い道のりです。
こうした現実を前にすると、私たちはあるジレンマに立たされます。
「文化を守るべきか、それとも資源を守るべきか」。
丑の日の食卓にウナギを並べることは、日本人の季節感を彩る伝統ですが、その一方で未来の川や海からウナギを奪いかねない。
源内のキャッチコピーが生んだ祭りが、二十一世紀には環境問題の象徴になってしまったのです。

江戸のコピーが残した贈り物と宿題
「本日土用丑の日」── 平賀源内のひらめきは、250年を経て、真夏の食卓にウナギを並べるという風習を残しました。
これは日本人の暮らしを豊かに彩った、まぎれもない「贈り物」です。
しかし同時に、資源の減少という「宿題」も託されました。
伝統を味わい続けたい気持ちと、未来にウナギを残さなければならない責任。
その狭間で私たちは揺れています。

もし何も変わらなければ、土用の丑の日は「ウナギを食べる日」ではなく、「ウナギを偲ぶ日」に変わってしまうかもしれません。
それでも、ウナギを食べる楽しみと、ウナギを守る努力は両立できるはずです。
「真夏のウナギ」という物語を次の世代に引き継ぐために ── 私たちには何ができるでしょうか。
参考文献・出典一覧
- WWFジャパン「シリーズ:ウナギをめぐって 人とウナギの歴史」WWFジャパン、2020年7月20日(2025年9月8日閲覧)
- キリンホールディングス「第6回 平賀源内と土用の丑の日~希代の才子が生んだ日本の慣わし~」キリンホールディングス(2025年9月8日閲覧)
- Histonary「平賀源内とうなぎの関係は?土用の丑の日はいつ?その起源は?」Histonary、2023年9月7日(2025年9月8日閲覧)
- みんなの知識 ちょっと便利帳「土用の丑の日の鰻 = 平賀源内はキャッチコピーを考えたのか? =」みんなの知識 ちょっと便利帳(2025年9月8日閲覧)
- サストモ「ウナギの旬は夏じゃない?5割は違法?今こそ知っておきたいウナギのこと」Yahoo! JAPAN SDGs、2025年9月8日閲覧
- 日本史トリビア「【平賀源内とうなぎ】土用の丑の日の仕掛け人」日本史トリビア(2025年9月8日閲覧)
- FOOD LAB「土用の丑の日からうなぎが消える?」三友、2024年3月1日(2025年9月8日閲覧)
- 弁護士JPニュース「絶滅危惧種「ニホンウナギ」が“食用禁止”にならないのはなぜ? 水産庁「絶滅のおそれはない」とするも…専門家が指摘“政府の立場”の「変化」とは」弁護士JPニュース、2025年7月18日(2025年9月8日閲覧)
- TRAFFIC「土用の丑の日にウナギについて考える」TRAFFIC、2011年7月12日(2025年9月8日閲覧)
- 水産庁「ウナギをめぐる状況と対策について」水産庁、令和7年6月(2025年9月8日閲覧)