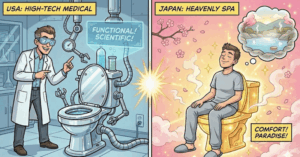なぜその日なのか?
「中秋の名月」とは、旧暦8月15日の夜に輝く月の呼び名です。
この夜を楽しむ風習は、日本では「お月見(十五夜/観月)」、中国では「中秋節」として知られています。
新暦に置き換えると、およそ9月中旬から10月初旬にあたります。年ごとに日付が動くのは、太陽のリズムで刻む新暦と、月の満ち欠けを基準にする旧暦という、二つの暦を行き来するためです。ちなみに2025年は10月6日がその日にあたります。
では、なぜ旧暦8月15日の月を「中秋の名月」と呼び、特別に愛でるようになったのでしょうか。
このあと、暦の仕組みと「なぜ中秋なのか」の答え、中国から伝わった観月の文化、日本で庶民に広まったお月見の風習、そして現代に受け継がれる意味を、順にたどっていきます。
少し歴史に寄り道しますが…… 月は気長に待っていてくれるでしょう。
なぜ「中秋」と呼ぶのか?中秋の月は本当に名月なのか?
なぜ「中秋」と呼ぶのでしょうか?
まずは暦の話から始めましょう。
旧暦では一年を四季に分け、さらに各季節を三つの月に区切ります。
春は1・2・3月、夏は4・5・6月、秋は7・8・9月、冬は10・11・12月。
そのうち季節の真ん中にあたる月 ── 春なら2月、夏なら5月、秋なら8月、冬なら11月 ── を「仲春」「仲夏」「仲秋」「仲冬」と呼びました。
つまり、旧暦8月は「仲秋」、すなわち秋の真ん中の月。
その15日は、まさに仲秋のど真ん中にあたります。
厳密にいえば「中仲秋」とでも呼ぶべきところですが、さすがに語呂が悪い。
そこでシンプルに「中秋」と呼ばれるようになったのです。
まるで入れ子人形マトリョーシカのように、「真ん中の真ん中」を指す言葉だといえるでしょう。

ここでふと「でも、なぜこの日の月が特別に美しいの?」と疑問に思われるかもしれません。
実はそこには自然の仕組みが関わっています。
唐代の文人・欧陽詹(おうよう せん, 755–800)は『全唐詩』にこう詠んでいます。
冬の月は霜繁くして甚だ寒い、夏の月は雲蒸して甚だ暑い、
秋八月の月は暑からず寒からず
つまり中秋の月は、まるで「ちょうどいい湯加減のお風呂」のように、絶妙なタイミングで姿を現すのです。
実際、この頃の月は北半球では観月に最も適した高度に昇ります。
夏の月は高すぎて首が痛くなり、冬の月は低すぎて建物に隠れがち。
中秋の月は、まるで「私を見て」と言わんばかりに、ちょうどよい角度で夜空に浮かんでいるのです。
さらに秋は台風シーズンを過ぎ、空気中の水蒸気も少なく、空気が澄んでいます。
月は毎月満月になりますが、中秋の満月が特別に美しく見えるのは、この天然のフィルター効果のおかげなのです。

つまり「中秋の名月」とは、暦のうえで「真ん中の真ん中」であり、自然条件的にも「最高の観賞条件」が揃った、まさに月見界の特等席。
古人たちは、偶然ではなく必然として、この日を選んだのです。
中国の宴、日本の雅 ── 月が結んだ文化
中秋の月見は、まさに国際的な文化交流の産物です。
その源流をたどれば、古代中国の観月習慣に行き着きます。
中国では古くから月を愛でる風習がありましたが、唐代(618〜907年)になると、文人たちの間で「月を眺めながら詩を詠む」という風流な遊びが大流行しました。
まるで現代のインスタ映えを狙うかのように、彼らは美しい月夜を背景に知的な宴を開いたのです。
やがてこの雅な遊びは宋代(960〜1279年)に定着し、「中秋節」として正式な行事になりました。
その際に生まれたのが、満月をかたどった丸いお菓子「月餅」です。
円い形は家族団欒の象徴。
お菓子にまで哲学を込めてしまうところに、中国らしさが表れています。
一方、日本では平安時代に遣唐使がこの文化を持ち帰りました。
最古の記録は漢詩人・島田忠臣(しまだのただおみ、828〜889年)の詩とされ、文徳天皇の時代(850〜858年)にはすでに、詩人たちが私的に観月の宴を開いていたと伝えられます。
興味深いのは、平安貴族の月の楽しみ方です。
彼らは月を直接見上げず、杯や池の水面に映る月影を愛でました。
まるで「直視は野暮、間接的に楽しむのが粋」とでも言うように。
この控えめで奥ゆかしい美意識こそ、平安貴族らしい雅な精神の表れだったのでしょう。

こうして中国で生まれた観月文化は海を渡り、日本独自の繊細さと奥ゆかしさをまとって根づいていきました。
文化とは、国境を越えてなお磨き上げられる、美しい贈り物なのです。
月に感謝、芋に感謝 ── 江戸の月見
貴族の風雅な遊びも、時代を下ると庶民の手に渡り、まったく違う姿を見せるようになります。
室町時代には、華やかな詩宴はしだいに簡素化され、月に手を合わせ、供物を捧げる素朴な形式へと変わりました。
まるで豪華なフルコースが、温かな家庭料理へと姿を変えるように。より実用的で親しみやすい行事になっていったのです。
そして江戸時代、月見は庶民文化として完全に花開きます。
ここで主役は詩歌から農作物へとバトンタッチ。
秋の実りに感謝する祭りとして、新たな生命を吹き込まれました。
とくに里芋を供えることから、この夜は「芋名月」と呼ばれるようになります。
なぜ里芋なのか? 答えは単純です。
中秋のころがちょうど収穫の時期だったから。
自然の恵みに合わせて感謝を捧げる ── 理にかなった風習です。
月見団子が登場するのは江戸中期以降のこと。
でも、ここにも地域差がありました。
関東では丸い団子をピラミッド型に積み上げ、関西では里芋の形を模した団子にあんこを巻く。
同じ月を見上げながら、関東は幾何学的、関西は自然志向。
お国柄の違いが団子にまで表れています。
供物はほかにも、すすき、枝豆、栗などがありました。
すすきは稲穂に似た形から豊作の象徴に。
枝豆や栗は秋の恵みへの感謝のしるし。
月見台は、まさに自然に宛てた感謝状を並べた祭壇だったのです。

東アジア、それぞれの月見
月を愛でる文化は、東アジアに共通する大切な財産です。
ただし、その姿は国ごとに少しずつ違い、個性豊かに発展してきました。
さっそく覗いてみましょう。
まず中国。いまも主役はやはり月餅です。
丸い形は家族団欒の象徴とされ、現代では「団欒節」とも呼ばれます。
離れて暮らす家族がこの日に集まる。
月餅ひとつに「みんな揃って」という願いが込められ、中国人の心を結んでいるのです。
韓国の秋夕(チュソク)は、日本のお盆に近い行事です。
墓参りと先祖供養が中心で、家族が一堂に会して祖先を敬う。
月よりも先祖が主役となるところに、いかにも儒教文化らしい色合いがにじみます。
台湾では文旦(ぶんたん)という柑橘が欠かせません。
さらに1980年代からはバーベキューが大流行し、伝統と現代が同居する独特の風景が生まれました。
ただ、月を見ながら肉を焼く姿を古人が見たら。
きっと腰を抜かすに違いありません。
ベトナムでは子どもが主役です。
灯籠を手にしたパレードが街を練り歩き、獅子舞が各家を訪ねます。
大人の風雅な行事から子どもの祭りへと変化したのも、文化の柔らかさを物語っています。

形はさまざまに変わっても、共通しているのは「満月への願い」です。
丸い月は円満を、欠けのない形は団結を象徴する。
国境を越え、同じ月を見上げながら、人類は同じ祈りを捧げているのです。
現代に生きる中秋の名月
LED街灯やデジタルサイネージに囲まれた現代社会で、月見はかつてとは違う意味を持つようになりました。
昔の人々にとって、月は夜道を照らす実用的な光源でした。
とりわけ中秋の名月は、豊作を祈る切実な対象。
生きるか死ぬかを左右する思いが、そこには込められていたのです。
一方、現代の私たちにとって月見は、意識的に暗闇と向き合う時間になりました。
街の明かりを忘れ、スマートフォンを置いて、ただ空を見上げる。
それは心を静かに満たす精神的な営みへと変化しました。
旧暦8月15日が「中秋の名月」に選ばれたのは、偶然ではありません。
暦の真ん中という象徴性、観月に最も適した自然条件、そして文化が磨き上げた美意識。
これらが重なって生まれた、必然の選択だったのです。
古人の洞察力には、いま改めて感服せざるをえません。
これで、歴史への寄り道はひとまずおしまい。
少し長い寄り道でしたが、月はきっと待っていてくれたことでしょう。
参考文献・出典一覧
- ウィキペディア編集コミュニティ 「中秋節」 ウィキペディア(2025年9月11日閲覧)
- China Highlights 「中秋節の食べ物」 China Highlights(2025年9月11日閲覧)
- China Highlights 「中秋節の挨拶によく使われる人気言葉を紹介」 China Highlights(2025年9月11日閲覧)
- China Highlights 「中秋節の歴史」 China Highlights(2025年9月11日閲覧)
- China Highlights 「中秋節の風俗習慣」 China Highlights(2025年9月11日閲覧)
- China Highlights 「中秋節の物語」 China Highlights(2025年9月11日閲覧)
- 水谷俊樹 「「中秋の名月」の起源と変遷を辿る【歴史にみる年中行事の過ごし方】」 note、2022年9月4日(2025年9月11日閲覧)
- 馬場あき子 「水面に映る望月にことさらな趣を感じた平安貴族【和歌で読み解く日本のこころ】」 和楽web、2024年9月5日(2025年9月11日閲覧)
- 株式会社山梨中央銀行 「中秋節とは?中秋の名月と同じ日。今年はいつ?日本の風習は?」 ふじのーと、2023年9月21日(2025年9月11日閲覧)
- 国立天文台 「名月必ずしも満月ならず」 暦Wiki(2025年9月11日閲覧)
- 国立天文台 「星空情報2025年10月 中秋の名月(2025年10月)」 国立天文台(2025年9月11日閲覧)
- 国立天文台 「月待ちは秋に限る」 暦Wiki(2025年9月11日閲覧)
- 国立国会図書館 「NDLイメージバンク 月見」 国立国会図書館サーチ(2025年9月11日閲覧)
- 伊勢神宮 「神楽祭・観月会」 伊勢神宮(2025年9月11日閲覧)