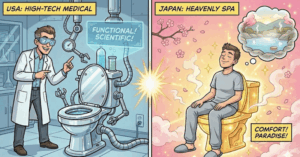七七・八八に隠された、日本人のユーモアと敬意
どうして77歳は喜寿(きじゅ)、88歳は米寿(べいじゅ)と呼ばれるのでしょうか?
祖父母のお祝いの席で耳にしても、その理由までは考えたことがない。
そんな方も多いはずです。
七や八という、ただの数字。
ところが昔の人は、その並びに「ある漢字のかたち」を見つけてしまったのです。
そこから、長寿を祝うユーモラスな呼び名が生まれました。
かつては七十七や八十八まで生きることが、奇跡に近い出来事でした。
人びとはその稀な幸運を、言葉遊びに託して敬意を表したのです。
「長寿祝い」とは何か
人の一生は、ただ年を重ねるだけではありません。
人生の節目ごとに「ここまで無事に生きてきた」ことを確かめ合う。
そのために生まれたのが長寿祝いです。
古くは「年祝い」や「賀寿(がじゅ)」とも呼ばれました。
奈良時代の貴族社会では、40歳を過ぎると10年ごとに祝宴を開きました。
そこには「厄をはらい、命を長らえたい」という祈りが込められていたといわれます。
平均寿命が30〜40歳ほどだった時代に、70や80を迎えることは、まさに神話級の長生き。
だからこそ「古稀(こき)」「喜寿(きじゅ)」「米寿(べいじゅ)」など、特別な名前を与え、社会全体でたたえたのです。
やがて室町時代には「還暦」という言葉が定着し、江戸時代には庶民にまで広がりました。
「長生きすること」自体がエンターテインメントとなり、家族や地域で盛大に祝う文化が根づいたのです。

では、具体的にどんな年齢が区切りとされてきたのでしょうか。
ここで一覧を見てみましょう。
賀寿の代表例(一覧)
- 還暦(かんれき・61歳) … 生まれた年の干支に還る「本卦(ほんけ)がえり」
- 古稀(こき・70歳) … 杜甫の詩「人生七十古来稀なり」に由来
- 喜寿(きじゅ・77歳) … 「喜」の草書体が「七十七」に見える
- 傘寿(さんじゅ・80歳) … 「傘」の略字「仐」が「八十」に見える
- 米寿(べいじゅ・88歳) … 「米」の字を分解すると「八十八」
- 白寿(はくじゅ・99歳) … 「百」から「一」を取ると「白」
ほかにも「卒寿(90歳)」「茶寿(108歳)」など、知恵と遊び心に満ちた呼び名が続きます。
喜寿(77歳)の由来
「喜」という字を草書体で書くと「㐂」と崩れます。
これがどう見ても「七十七」に読める ── それが喜寿の名前の由来です。
いわば、漢字がひとりで勝手に「77歳おめでとう」と祝ってくれているわけです。

喜寿のテーマカラーは紫。
高貴さを象徴する色であり、「人生七十七年の重み」を纏うにふさわしいとされてきました。
もっとも江戸時代の平均寿命は40歳前後。
77歳まで生きるのは奇跡に近く、現代でいえば120歳を迎えるくらいの驚きだったかもしれません。
まさに「稀有な長寿」だったのです。
米寿(88歳)の由来
「米」という字をよく見ると、八十八に分解できます。
そこから「米寿」。
なんとも日本らしい発想です。

しかも稲穂の黄金色と重ね合わせて、米寿のシンボルカラーは金茶色。
田んぼに垂れる稲穂のように、人生の実りを祝う色です。
米は古来、日本人の命の糧であり、神事にも供えられてきました。
だからこそ「米寿」は単なる数字遊び以上の意味を持ちます。
米を支えに生きてきた人生八十八年を、社会全体で称える ── そんな文化的背景が見えてきます。
他の賀寿の例
喜寿や米寿ばかりが有名ですが、ほかにも知恵と遊び心に満ちた呼び名があります。
- 古稀(こき・70歳)
唐の詩人・杜甫が詠んだ「人生七十古来稀なり」に由来。実際、杜甫自身は70歳に届かず亡くなったので、皮肉といえば皮肉です。 - 傘寿(さんじゅ・80歳)
「傘」の略字「仐」が「八十」に見えることから。長寿の祝いに「傘」を贈るのも、粋なしゃれです。 - 白寿(はくじゅ・99歳)
「百」から「一」を引くと「白」になる。99歳まで生きたら、もはや白髪どころか仙人の域でしょう。
こうして眺めてみると、長寿祝いはただの迷信や儀式ではなく、文字と文化を掛け合わせた知的な遊びであったことがわかります。
人は老いをただ恐れるのではなく、笑いや敬意をまとわせて受け止めてきたのです。
昔の奇跡が、今は日常に
昔なら「77歳?88歳?それは仙人の話だろう」と笑われたかもしれません。
ところがいまでは、その年齢を迎える人がご近所にごく普通にいらっしゃいます。
戦後の日本は医療と衛生の劇的な発展で寿命をぐんぐん延ばし、いまや平均寿命は男女とも80歳を超えました。
かつて「古来稀(こき まれなり)」とされた年齢が、日常の風景に溶け込むようになったのです。
杜甫が見たら、「稀どころか、あふれているではないか」とぼやいたに違いありません。
こうした長寿を祝う文化は、現代社会でも「敬老の日」として受け継がれています。
9月の第3月曜日 ── 忙しい日本人にとってはありがたい三連休の一日ですが、本来は「多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬い、長寿を祝う」日。
1947年(昭和22年)に兵庫県の小さな村で開かれた敬老会が、全国的な祝日へと発展したのですから、人を敬う心の力は侮れません。

さらに21世紀に入ると、「緑寿(ろくじゅ・66歳)」「茶寿(ちゃじゅ・108歳)」といった新しい賀寿も登場しました。
たとえば「茶」の字は「十・十・八十八」に分解できるので108 ── もはやクロスワードパズルの域です。
こうして眺めると、長寿祝いは単なる年齢の区切りではなく、時代ごとの寿命や価値観を映す鏡だといえます。
平均寿命が伸びれば、新しい賀寿が生まれる。
言葉と文化の柔軟さこそ、日本人のしたたかなユーモアなのです。
長寿を祝う言葉は、相手への贈り物であり自分への問いでもある
喜寿や米寿の背後には、「長く生きてこられたことへの敬意」と「祝福の気持ち」が息づいています。
数字と漢字を重ねた洒落が、やがて人生の節目を彩る大切な文化となりました。
日本人は老いを恐れるばかりでなく、そこにユーモアと敬意を織り込みながら受けとめてきたのです。
次に大切な人がこの節目を迎えたとき、あなたはどんな言葉を贈るでしょうか。
それは相手への敬意を形にする小さな実践であり、同時に私たち自身が人を大切にする感性を磨く機会にもなります。
さらにこれは、未来の自分への問いかけでもあります。
自分がその年齢に達したとき、どんなふうに祝われたいか。どんな時間を歩んでいたいか。
喜寿や米寿という呼び名を知ることは、単なる雑学にとどまらず、人生をどう生きるかを考えるヒントになるのです。
参考文献・出典一覧
- 色彩歳々 編集部「長寿祝い・年祝い(還暦など)──長寿祝い・年祝いは何歳から?何をするの?」色彩歳々、2025年9月14日閲覧
- ウィキペディア日本語版編集者「賀の祝い」ウィキペディア日本語版、2025年9月14日閲覧
- ウィキペディア日本語版編集者「年齢」ウィキペディア日本語版、2025年9月14日閲覧
- 小さな資料室 編集部「資料14:杜甫の詩『曲江』──「古稀」の語の出典」小さな資料室、2025年9月14日閲覧
- 厚生労働省「平均寿命の国際比較(令和6年)」厚生労働省、2025年9月14日閲覧
- 内閣府「各「国民の祝日」について──敬老の日」内閣府、2025年9月14日閲覧
- 内閣府「「老人の日・老人週間」キャンペーン」内閣府、2025年9月14日閲覧
- ウィキペディア日本語版編集者「敬老の日」ウィキペディア日本語版、2025年9月14日閲覧
- 本川裕「平均寿命の歴史的推移(日本と主要国)」社会実情データ図録、2025年9月14日閲覧