世界はなぜでできている– category –

-
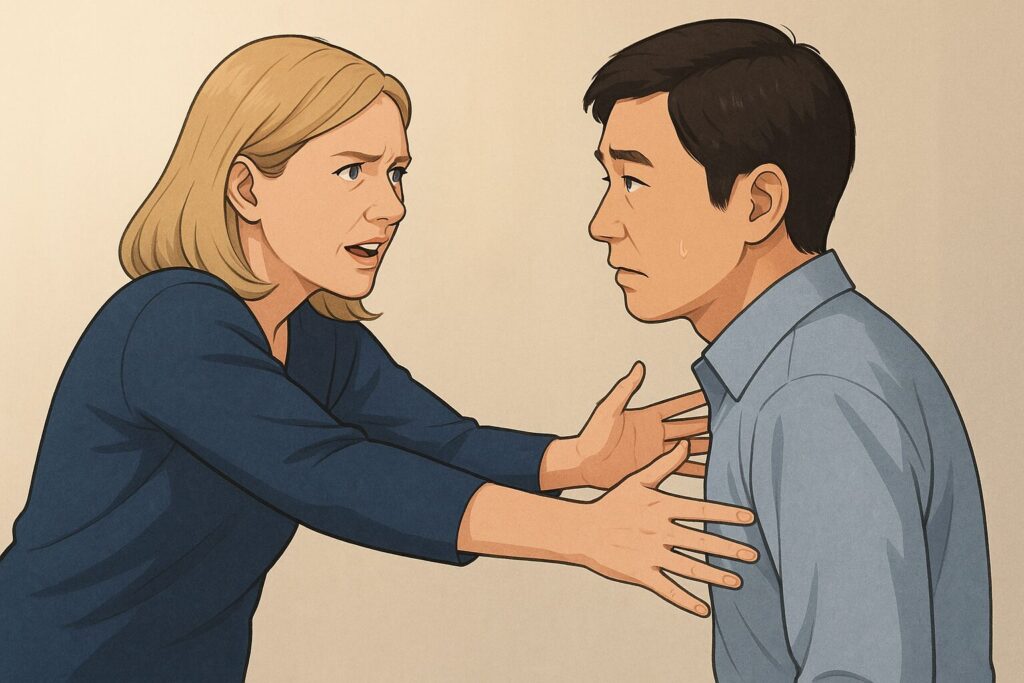
なぜ日本人はハグが苦手なのか?~西洋の「触れて絆を作る」文化と、日本の「絆があるから触れる」文化の違い~
あなたは、ハグが得意ですか? わたしがまだ10代後半の頃、近所にペルー人の夫婦が住んでいて親しくしていました。毎週のように一緒に食事をし、やがてご主人のお姉さんとも親しくなりました。 あるとき、夕食後にお姉さんが帰宅する際に、突然満面の笑み... -
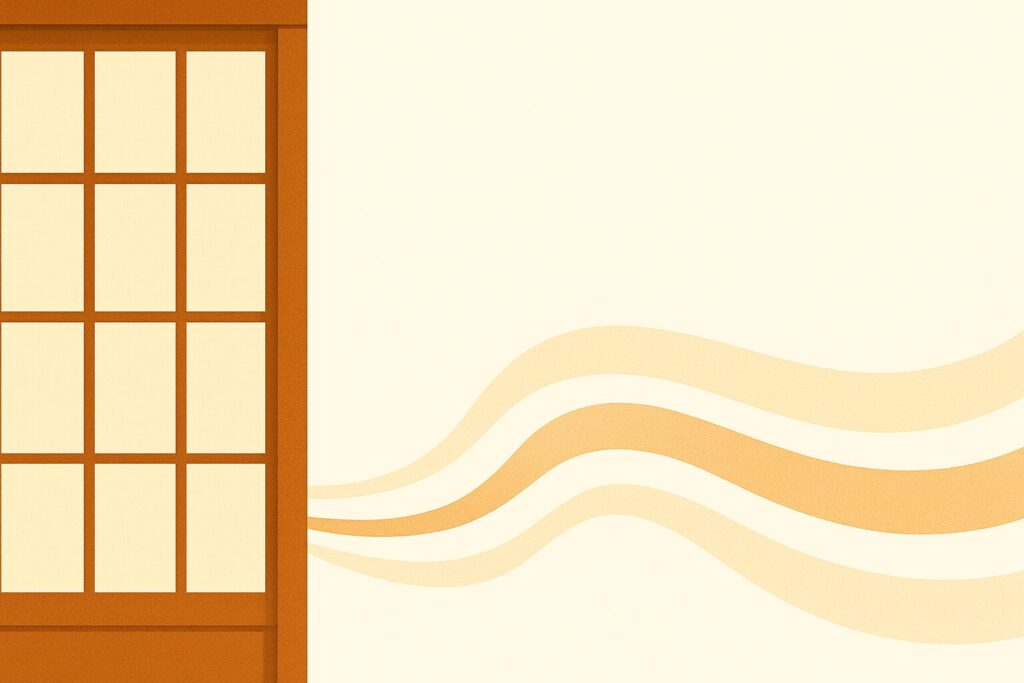
なぜ日本人は「無臭」にこだわるのか?~縄文の昔から現代まで続く、日本の独特な匂いの文化~
「匂い」が気になる国、日本 あなたは今日、誰かの「匂い」が気になりませんでしたか? エレベーターで鼻をつく香水、オフィスで漂う同僚の柔軟剤、夏の満員電車の体臭。 日本人は、匂いに対して年々敏感になっています。いや、もしかすると、昔からずっと... -
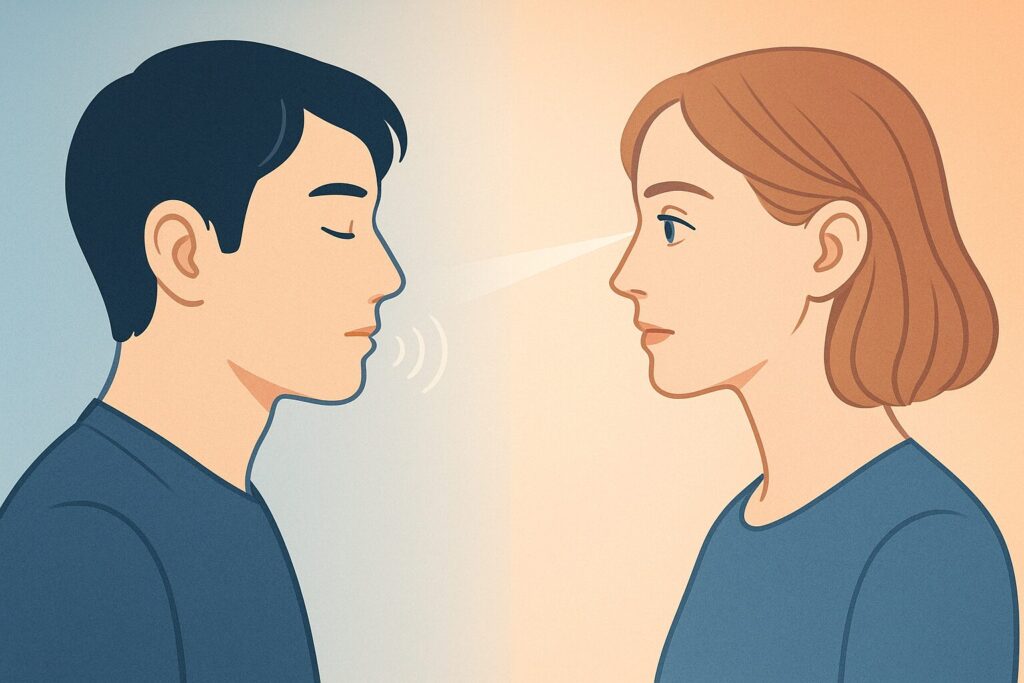
なぜ日本人は「聞く」文化、西洋人は「見る」文化と呼ばれるのか?
あなたは誰かと話すとき、相手のどこを見ていますか? 日本人は「聞く」文化、西洋人は「見る」文化。 こんな言葉を耳にしたことはありますか。これは、それぞれの国の人々がどのように会話を理解しているかを表す言い方です。 その意味をかみ砕くと、こう... -

なぜ漢字の世界とアルファベットの世界では、ものの「見え方」が違うのか?
あなたが見ている世界は、本当に隣の人と同じですか? ちょっと考えてみてください。 休日、駅で待ち合わせた友人を人混みの中から探すとき。あるいは、スーパーの棚にずらりと並ぶ商品の中から、いつもの調味料を見つけるとき。 この「見て」「探す」とい... -

なぜ日本人は「すみません」を「ありがとう」の意味で使うのか?~無意識の習慣から戦略的な選択へ~
通勤電車の中の「すみません」— 無意識の口癖 満員電車で肩がぶつかる ──「すみません」。降りる人に道を譲られて ──「すみません」。駅員に道を尋ねて教えてもらうときも ──「すみません」。そして、コンビニのレジで商品を受け取る瞬間にも、思わず口を... -

なぜ虹の色は、日本では7色、アメリカでは6色、ドイツでは5色なのか?~言語と文化が変える世界の見え方~
虹は七色ではない?── 色の数が国によって違う、驚きの文化差 子どもの頃、雨上がりの空に虹を見つけて、「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」と指を折りながら数えた記憶はありませんか?日本人にとって虹は「七色」── これは疑いようのない常識です。 ところ... -

なぜ私たちは渡り鳥を見ると郷愁を感じるのか? ~日本人が渡り鳥に重ねてきたもの~
秋空を渡る声が、なぜ胸を締めつけるのか 東京ではもう、渡り鳥なんて見られない ── そう思っていませんか。実は、そうでもないのです。 葛西海浜公園。ここは、湾内で唯一ラムサール条約に登録された湿地のある公園で、毎年、シベリアなどから数万羽の渡... -

なぜ渡り鳥はV字編隊で飛ぶのか?~自然界が実践する「最強のチームマネジメント」~
V字飛行が語る知恵 子どものころ、わたしは神奈川県の小さな町で育ちました。秋が深まると、夕暮れの空に渡り鳥たちが列をなして飛んでいくのを、よく見上げたことを思い出します。 薄い光の中、きれいなV字の形を保ちながらゆっくりと進んでいく姿。その... -

なぜ渡り鳥は道に迷わないのか?~地図もGPSも持たない旅人の秘密~
もしあなたが、地図もスマホも持たずに大陸を越えろと言われたら? 想像してみてください。ある日突然、「地図もスマホもなしでアジア大陸を横断してみろ」と言われたら。きっと三日も経たずに、コンビニもWi-Fiもない場所で立ち尽くしてしまうでしょう。 ... -

なぜ江戸の人々は伝統色「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃ ひゃくねずみ)」を生みだしたのか?~江戸の「粋」は現代の「ミニマリズム」に通じていた~
色を奪われた人々が、生み出した「無限の色」 「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃ ひゃくねずみ)」。 この言葉を初めて目にしたとき、正直、読み方さえ分かりませんでした。でも調べるうちに、江戸の人々の不屈の強さと、その奥に息づく繊細な美意識に、深... -

なぜ私たちは「旬」という小さな言葉に心を動かされ続けるのか?
秋、旬の国へ。 秋は、食卓がいちだんと賑やかになる季節です。里芋、さつまいも、松茸、銀杏。柿、梨、りんご、ぶどう。そして、何と言っても炊き立ての新米。 この顔ぶれを眺めるだけで、胃袋が思わず拍手を始めます。 日本人にとって「旬」とは、ただの... -

なぜ日本には1,100もの伝統色があるのか?~現代人にこそ必要な、違いを感じ取り、言葉にする力~
あなたは「緑」をいくつ言えますか? 萌黄(もえぎ)、若草(わかくさ)、鶸(ひわ)、常磐(ときわ)、若竹(わかたけ)──。どれも同じ「緑」なのに、微妙に表情が異なります。萌黄は春の息吹、若草はやわらかな陽光に笑う草、常磐は凛とした冬の松。その...