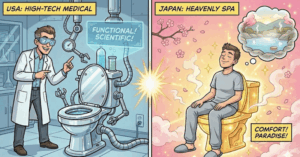「食欲の秋」は気のせいじゃない
「どうして秋になると、最初の一口がいつもよりもおいしいのだろう」。
それは気のせいではありません。
私たちの身体には、季節の変わり目を感じて静かに準備を始める「内なる暦」があります。
朝夕のひんやりした空気に触れると、体温を守ろうとからだは燃料を集め、短くなる日照は脳の化学バランスを少しずつ変えていく。
結果、自然と「もう一口」が欲しくなるようにできているのです。
同時に、秋の台所は開け放たれた宝石箱のようです。
旬を迎えた色とりどりの食材が五感をいっせいに呼び覚まし、「新もの」と「秋限定」の前では理性より先に箸が動きます。
さらに日本の秋には、人々を食卓へと誘う仕掛けがいくつも隠れています。
この時期のさまざまな行事が、自然と人々を同じ食卓へと集めるのです。
つまり秋に食欲が高まるのは、体の仕組みと文化の記憶が同時に働くから。
ではこれから、この2つが相互に響き合うしくみをひもといていきましょう。
秋は「冬支度の助走」— 身体が先に反応する
秋が深まると、からだは静かにギアを上げます。
朝晩の涼しさに触れるたび、わたしたちの「内なる暦」—— 神経物質やホルモンたち —— が「そろそろでは…」と身体に合図を送るのです。
まずは、セロトニンとメラトニン。
セロトニンは主に日中に活性が高まる神経伝達物質で、食欲にブレーキをかける役割があります。
秋に日照が短くなるとこのブレーキが弱まり、甘いものや炭水化物に手が伸びやすくなります。
一方メラトニンは、暗くなると増える「そろそろ寝る時間」の合図を出すホルモン。
秋は夜の訪れが早く、このスイッチが前倒しになるため、日中の覚醒感が落ち、夕方から夜にかけての空腹感が強くなりやすい。
覚醒感が落ちるとブレーキ役のセロトニンが下がり、脳は手早く手に入る燃料=糖質を求めやすくなるのです。
さらに、他のホルモンたちも一役買います。
空腹時に高まるグレリン(食欲増進ホルモン)は、秋冬に活性が高まるという報告があり、これが食欲を後押しする可能性があります。
レプチンという食欲抑制ホルモンの方は、血中量や効果の季節差について研究間で結果が分かれており、秋に低下する=食欲が高まるとは現時点では断定できません。
別の、コルチゾール(ストレスに対処するために増えるホルモン)は、秋冬に活性が高まるという研究があります。
これが高い状態が続くと、手っ取り早く手に入るエネルギーを求めて、甘いものや脂の多い料理を選びやすくなります。
総じて、秋は複数のホルモンが重なって「食欲を高める」方向に働きやすい季節です。
人がカレンダーをめくる前に、内なる暦の方が先に秋を察しているわけです。

※注意:感じ方には個人差・地域差があります。
年齢、睡眠、活動量、空調・照明など生活環境によっても様相は変わります。
誰もが同じ強さで「秋=食べ過ぎ」になるわけではありません。
実りの季節が背中を押す — 旬・新もの・五感
秋は、旬が同時多発する季節です。
米は立ち、きのこは香り、芋や栗は甘みを増し、新物の魚は脂のノリが最高潮に達します。
まるで食材たちが一斉に「今こそ本番!」と名乗りを上げるのです。
並べて炊けばほくほく、焼けば皮がはぜ、切ればみずみずしい。
季節は、理屈より先に「いまが食べごろだ」と説得してきます。
そこへ追い風となるのが、「新米」「新そば」「新酒」といった“新もの”の旗印です。
人は「新」や「初」の一字に弱いもの。
理性と願望の審議なんて、「新」の一声であっさり打ち切りになるのです。

そして仕上げは五感の共鳴です。
空気がひんやりすると、温かい料理は「ちょうどいい温度帯」に収まり、香りの立ち上がりが一段と冴えます。
湯気が視界をやわらげ、鼻先をくすぐられて、手は自然に箸へと伸びる。
味覚だけではありません。
嗅覚と温度感覚も加えた合奏が最高潮を迎え、食欲という指揮者が一段と激しくタクトを振るのが秋なのです。
行事が食べる日を増やす — 秋は集まる口実が多い
秋は、何かと集まる予定の増える季節。
日にちが定まると、人はそこから逆算して買い出しをし、人数分より少し多めに用意します。
大鍋や大皿が並べば、おかわりはほぼ既定路線。
これだけで一回あたりの食べる量は上がります。
行事もたくさんあります。
お月見(十五夜・十三夜)なら団子や里芋や栗が並びます。
秋祭りや収穫祭では屋台がずらり。
焼き物の匂いとはぜる音の誘惑が強烈です。
東北の芋煮会は河原で大鍋を囲む定番で、「もう一杯どうぞ」が合言葉。
各地の新そば祭り・新米のお披露目・さんま祭りも、この季節の「限定モノ」が次々にやって来ます。
学校行事も重なります。
運動会、文化祭、大学祭の模擬店は「食べ歩きコース」そのもの。
都市部では百貨店の秋の物産展やひやおろし/新酒の催しが相次ぎ、「飲む+つまむ」がセットになります。
週末ごとに食べる口実が積み上がっていくのです。

どうして秋に食欲が高まるのか。
理由はシンプルです。
まず回数が増える(予定が多い)。
次に量が増える(持ち寄り・差し入れ・大鍋は「少し多め」が普通)。
さらに断りづらい(すすめ合う、取り分ける、乾杯する)。
そこへ匂いと音の刺激(焼ける匂い、はぜる音)が重なり、
過ごしやすい気候が外食や屋外イベントを後押しします。
カレンダーに予定が一つ増えるたび、普段の自制は一歩下がり、食卓の皿も一枚増える。
結局は、これが「食欲の秋」の本当のカラクリなのかもしれません。
身体の必然、文化のご褒美
では、ポイントをふり返ってみましょう。
秋は日照が短くなってセロトニンのブレーキが弱まり、メラトニンが前倒しになって糖質志向に傾きやすくなります。
そこへグレリン(空腹サイン)やコルチゾール(ストレスホルモン)の上振れが重なり、「もう少し」を後押しします。
いっぽう社会では、旬の重なりと行事・催しが予定と食材をそろえ、食べる回数と量が増えやすくなる。
涼しさも手伝い、温かい料理の旨さが一段と引き立つ時期です。
つまり、身体の必然(光・温度・脳化学・代謝)と、文化のご褒美(旬と行事)の両方が同じ方向を向くのが秋です。
食欲の秋 — この言葉は、季節の気分を一語に凝縮し、胃袋のカーテンを開け放つ合い言葉なのです。
参考文献・出典一覧
- コトバンク編集部「食欲の秋」コトバンク(2025年9月19日閲覧)
- Noriko Tanaka, Toyoko Okuda, Hisae Shinohara, Rie Shimonaka Yamasaki, Naomi Hirano, Jangmi Kang, Manami Ogawa, Nao Nishioka Nishi「Relationship between Seasonal Changes in Food Intake and Energy Metabolism, Physical Activity, and Body Composition in Young Japanese Women」Nutrients、2022年1月22日
- Kyoko Fujihira, Masaki Takahashi, Chunyi Wang, Naoyuki Hayashi「Factors explaining seasonal variation in energy intake: a review」Frontiers in Nutrition、2023年7月21日
- Clare L. Adam, Julian G. Mercer「Appetite regulation and seasonality: implications for obesity」Proceedings of the Nutrition Society、2007年3月7日
- Shaina Cahill, Erin Tuplin, Matthew R. Holahan「Circannual changes in stress and feeding hormones and their effect on food-seeking behaviors」Frontiers in Neuroscience、2013年7月7日
- Nicole Praschak-Rieder, Matthaeus Willeit, Alan A. Wilson, Sylvain Houle, Jeffrey H. Meyer「Seasonal variation in human brain serotonin transporter binding」Archives of General Psychiatry、2008年9月
- G. W. Lambert, C. Reid, D. M. Kaye, G. L. Jennings, M. D. Esler「Effect of sunlight and season on serotonin turnover in the brain」The Lancet、2002年
- Oana-Maria Bîrlea「Japan’s Food Culture – From Dango (Dumplings) to Tsukimi (Moon-Viewing) Burgers」East-West Cultural Passage、2021年5月12日(2025年9月19日閲覧)
- 農林水産省「Traditional Dietary Cultures of the Japanese」農林水産省(2025年9月19日閲覧)